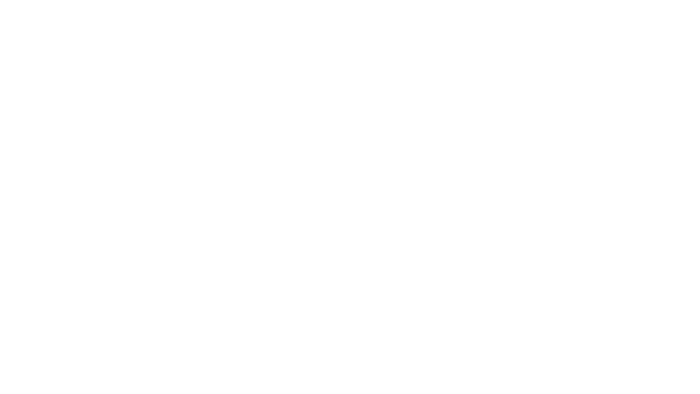

〔札幌〕北海道大学大学院農学研究院の清水池義治准教授は、今秋から本格化する次期酪肉近代化基本方針の見直し議論について「現行生乳生産目標の780万㌧(2030年度)という数字を下げるのは、生産者のマインドに大きな影響を与える」と指摘した。その上で、「目標を具体的にどう実現するのか、実効性のある手段とセットの議論が必要」と強調。私案として、需要拡大が見込めるチーズ振興策や酪農家への直接支払い制度創設などを提言した。酪農乳業速報のインタビューに答えた。(【連載】新酪肉近への期待とポイント③)
―新たな酪肉近で注目している点はどこでしょうか。
「良くも悪くもやはり、目標数量には関心が集まるのではないでしょうか。現行の780万㌧という目標も、策定当時はそれなりのインパクトを持って受け止められたと思いますが、今回の議論でもその数字は大きな意味があります。目標については、780万㌧という現行の数字を下げるのは問題です。下げることにより、生産者のマインドに与える影響が大きいためです。頑張る必要がないというメッセージになり、例えば現在の生産量(23年度733万㌧)よりも多い水準を掲げたとしても、目標を下げるというのは生産現場に良い影響を与えません。一方で需要が芳しくない状態で数量を維持するという点では、政策的に矛盾します。生産を増やしても需要面で問題がないよう政策的に担保する。だから意欲的に生産してほしいという方向性がベストだと考えます」
「世界的に見ると、乳製品需要は旺盛です。ある分析では、今後10年で80万㌧の脱脂粉乳需要の増加が見込まれるとの予測もあります。一方で供給面に目を移すと、オセアニアや欧州は環境規制や生産基盤の面を含めて増産が難しそうな状況です。需給は逼迫、国際乳製品市場は引き締まり、価格的に上昇していくことも見込まれます。その中で、日本が乳製品を安定的に輸入し続けられるかどうか。そう考えるとやはり、乳製品に限らず言えることですが、国内で生産できるものは国内で生産すべきという観点が重要になってきます。そうした点からも、780万㌧という目標数量は維持すべきで、輸入品と置き換えていく方向、国内で780万㌧を生産したとしても過剰とならないような仕組みを整備する方向性が大事だと考えます」
―目標数量の設定もさることながら、その実現に向けた具体策の議論も重要だということでしょうか。
「個人的には、名目的に掲げるだけで手段を伴わない目標数量には意味がないと感じています。目標に実効性を持たせるため、具体的な方策も示すべきです。例えば780万㌧だとするならば、40万㌧を今後増やすためにどうするか、どのくらいの予算が必要かといったことも具体的に議論すべきです。私は、そのための方向性としてやはり、チーズに可能性があると考えます。チーズで段階的に40万㌧増やしていくと言えば、乳業メーカーも設備投資など計画を立てやすくなります」
「需要が低下しているとはいっても、乳製品を輸入しているわけで、その意味で生乳は足りていません。私は現在輸入している生乳換算400万㌧分を増やそうと言っているわけでも、100万㌧増やそうと言っているわけでもありません。40万㌧程度増やそうと言っているのです。輸入分の1割を国産に置き換えたとしても、製品としてのチーズに換算すればそれほど膨大な量ではないはずで、海外からも理解は得られるのではないでしょうか。内外価格差が縮小している今だからこそ、推進すべきタイミングだとも考えます」
―国産チーズの増産に向けては、どのような対策が考えられるでしょうか。
「価格面で競争可能な水準とするためには、チーズ向け乳価を引き下げることが必要になりますが、完全に下げるわけではなく、増やした分だけ下げる形が考えられます。例えば、チーズ向け乳価が1㌔当たり80円、基準年のチーズ向け乳量が40万㌧だとして、そこから増えた2万㌧分の乳価だけ40円にするといった形です。チーズを増やしたい乳業メーカーにとってはメリットになります。ただその場合、単純に考えれば酪農家の手取り乳価は下がります。そこで必要になるのが直接支払いで支える仕組みです」
―直接支払いの必要性は以前から指摘されていますが、具体的にどんな仕組みを想定しているのでしょうか。
「チーズ向けという点で、当初は基本的に北海道の酪農家が受け取ることになりますが、ゆくゆくは都府県の酪農家も受け取ることができるよう変えていきます。飲用需要を満たすためには当然、都府県の生産を維持しなければなりません。価格が下がった分やコスト上昇分を補填する直接支払いが制度としてあれば、支えることができます」
「将来的にはその制度をベースとし、加工原料乳生産者補給金や配合飼料価格安定制度に基づく補填金など既存の制度も統合していく。さらに、その制度下で直接支払いの基準単価を決めた上で、自給飼料生産や国産飼料を利用している場合、環境配慮やアニマルウェルフェア、6次産業化、教育ファームに取り組んでいる場合など、さまざまな要素ごとに単価を上乗せしていくことも考えられます。いろいろな対策が複雑に絡み合っている今は、細かい要件のチェックなどにも労力が必要です。何かあった場合の緊急対策は別ですが、土台の対策をしっかり構築し、さまざまな要素を紐づけていく方がシンプルで分かりやすいと思います。酪肉近の議論でも、こうした大きな制度のあり方なども含めて考えるべきではないでしょうか」
―食料・農業・農村基本法が改正されましたが、酪肉近議論に与える影響を含め、どう捉えていますか。
「改正基本法についてはやはり、『食料安全保障』というキーワードが明記されたことに意味があると感じています。何らかの法律や制度を構築する際、食料安保の推進を目的とするものだと説明でき、酪農家への直接支払い制度もそれが目的だと言えます。構築できる政策の幅が広がったのではないでしょうか」
―今後の酪農界についてどのように見ていますか。
「一定程度の離農が見込まれる中、生乳生産の維持にはやはり規模拡大が必要です。ただ、そのための投資が難しい状況もあり、乳価や国の対策で後押しする必要があるでしょう。一方で自給飼料の振興も重要です。例えば子実トウモロコシを生産していたら単価を上乗せするなど、ここに直接支払い制度を関連づける形も考えられます」
「人手不足も課題です。牧場従業員はもちろんのこと、自給飼料を生産するためにも技術を持った人が必要です。雇用条件の整備、居住環境や地域のインフラ整備を含めた農村対策も重要になります。今後は、酪農家を支える総合サービス業のようなものも必要なのではないでしょうか。酪農ヘルパー、育成預託、コントラクター、TMRセンターなどを一体的に運営する。道内ではそれに近い形になっている農協もありますが、酪農に関することならなんでもできるプロフェッショナルな人材がそろったアウトソーシング会社のようなものを整備する必要もあると思います。新規就農者にどれだけ寄り添えるかも重要です」
―乳業のあり方についてはどう考えますか。
「酪農現場の課題解決にどこまで向き合えるかという観点が重要になります。北海道では農協などがしっかりした取り組みを進めていますが、都府県では生産者組織が弱体化している地域もあります。そうしたところに、乳業がこれまで以上に直接関わっていく。乳価などだけでなく、人やサービス面でまだまだ関わることができる余地があります。極論を言えば、先ほどのアウトソーシング会社のようなものを乳業が経営してもよいのではないでしょうか」
―最後に、酪肉近議論に期待する点をお聞かせください。
「目標数量や理念も重要ですが、やはりそれを具体的にどう実現するのか、実効性のある手段とセットの議論が必要です。課題が山積する今だからこそ、酪農乳業関係者がこれなら実現できると思える計画、画餅とならない計画を策定してほしいと思います」

