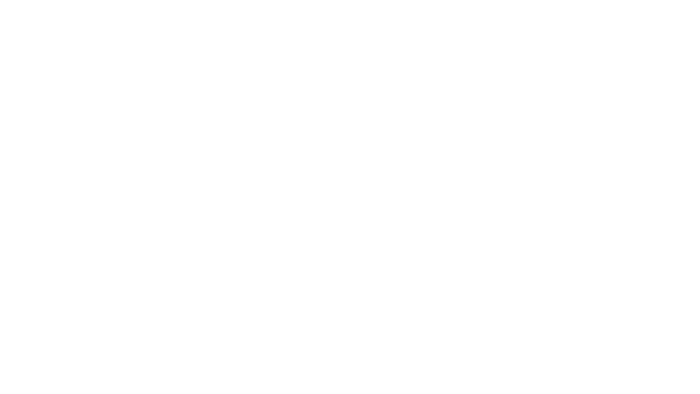

アイルランドの大手乳業メーカー、カーベリー社のリンダ・ターナーR&D(研究開発)マネージャーは酪農乳業速報のオンラインインタビューに応じ、「独自のスターターカルチャーにおける知見を活用しながら、日本のユーザーが求める高品質ナチュラルチーズ(NC)の開発に一層注力していきたい」と意欲を示した。日本向けに開発したNC「ウマミゼン」をはじめ、ユーザーの要望に応える商品提供に力を入れていく考えも強調した。

インタビューに応じたリンダ・ターナーR&Dマネージャー
―カーベリー社は、アイルランド南部の西コーク地方に製造工場を構え、地域で営農する家族経営を中心とした酪農家約1200戸から、年間約5億7400万㍑の生乳を集荷しているそうですね。
「生乳の多くはNCに加工しており、その生産量は年間約6万㌧に上ります(売上高は約6億6800万ユーロ)。日本向けには、チェダー、モッツァレラを中心に年間約3000㌧を輸出しています」
「チーズ作りにあたっては、独自のチーズカルチャーをキープしています。カルチャーは生乳の脂肪分や糖分、タンパク質などに作用しチーズのフレーバーを形づくります。その研究は50年に及び、独自のカルチャーでチーズ作りに臨むことが、私たちのビジネスの基礎であり『DNA』です。チーズカルチャーのレベルを引き上げるために、専門技術を備えたスタッフをそろえ、最新の技術を導入するなど絶えず投資を続けています」
「アイルランドでチーズを製造する企業の中で、スターター・補助カルチャーの両方を自ら培養しているのは当社だけで、研究・開発はアイルランド国立大学コーク校と連携し行っています。当社のチーズは進化を続けており、新しいカルチャーを作り出すことでフルーティーだったりナッツの風味を備えたり、あるいは甘み・旨味の強い商品を開発可能になりました。独自の知見によって、多様化するニーズに応える商品づくりを実現しています」
―日本のチーズ市場の傾向とはどのようなものでしょうか。
「日本の消費者の間では、旨味が強かったり、フルーティーだったり、ナッツ系のフレーバーを備えたりするタイプが好まれると私たちは認識しています。日本ではプロセスチーズ原料としての使用のほか、スナックとして、おやつやお弁当のおかず、おつまみなどとして食べるケースも広がっています」
「日本のチーズ市場は、まだまだ成長・拡大の可能性を秘めています。単なる栄養摂取源としてだけではなく、食卓を一層豊かにするアイテムとしてチーズを活用する傾向もあると感じています。洋食にとどまらず和食の材料としてチーズを取り入れるケースも増えてくるのではないでしょうか」
「チーズ消費のトレンドとして、欧州に目を向けると、プロテイン含有量が非常に高いタイプの需要が高まっています。日本でも同様のニーズが増える可能性があります。脂肪含有率が低い反面、タンパク質含有量の高いリデュースファットタイプのチーズについて、当社は英国とアイルランドで最大の『低脂肪チーズ』製造会社であり、他の追随を許さない商品開発力・供給力を備えていると自負しています」
―日本市場向けに、チェダータイプの「ウマミゼン」を開発しました。特長を教えてください。
「ウマミゼンは日本市場に向け、フレーバーが豊かで旨味が豊富なチーズが必要との依頼をいただき、開発に着手しました。2019年に実施した日本での市場調査を参考に、20年から翌年にかけてレシピを改良しフレーバーなどに一層磨きをかけました。1年を通じ安定した品質を維持できるかなどを検証した上で、23年後半から本格的な販売を開始しています」
「小売業向けにスナックとして食べていただく形で提供を始め、その後はプロセスチーズの原料として活用されたり、外食産業でもピザなどに使用されたりして販路が広がっています。商品名は当社が拠点を構えるアイルランドの西海岸側にあるミゼン半島の豊かな自然にちなんで命名しました」
―今後、日本市場でどのような取り組みを展開していきますか。
「取引先には、当社の商品開発能力や企業としての特徴、専門性に関する理解が深まっていると思っています。さらなるコラボレーションの展開に期待しています。実際、新しいプロジェクトも進行中です。日本のチーズ市場の拡大は、当社の成長に向けたチャンスでもあります。アイルランドや英国を含め健康意識の高まりが大きなトレンドとなっており、タンパク質の摂取源としてチーズが改めて見直されています。高齢化社会の中、良質のタンパク質摂取源であるチーズを提供できる点も私たちの強みです。日本市場では、こうした健康価値の訴求も行っていきます」


